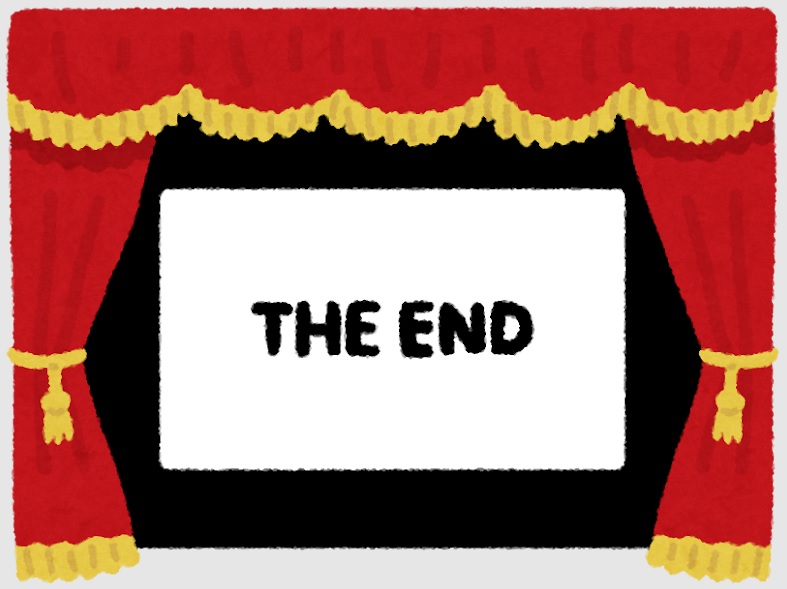管理人オススメコンテンツはこちら
「もったいない|確率無視の無意味な議論に終止符を」
〜前回のつづき〜
●確率を無視した議論は、ただのSF~数字を持ってこい、数字を~

「国が崩壊したらどうするんですか?
可能性は有りますよね?」
「そりゃ可能性は有るけど」
ってそれを言い出したら
「明日死ぬ可能性も有りますよね?」
とか
そんな話になってきちゃうんですよ。
あと
「家をもし貸してくれなくなったら
どうするんですか?」
みたいな。
貸してくれる事も
あるかもしれないけど
貸してくれない事も
確かに有るかもしれない。
でも貸してくれる事も
有るかもしれない。
あと
「今後インフレが進んだら
持ち家じゃないと損ですよね?」
とか
「私の投資は利回り20%で
運用出来てますよー。
インデックス投資なんて
せいぜい6〜7%ですよね?
私の投資はこういうふうにやったら
利回り20%で運用出来てますよー。」
みたいな。
それは
『確率』を無視してますよね?
なので『幅』か『確率』か
どっちか無視してるような話は
いくら議論したって
意味が無いんですよ。
●確率無視の対策は、ただの高額な自己満足~不安にカネを溶かすの、そろそろやめよう~

コストパフォーマンスの悪い対策は
もったいないんですよ。
「国が崩壊したら・・・」
と言っても
コストパフォーマンスのいい
対策が無いんですよ。
国が崩壊するという事の
コストパフォーマンスのいい
対策が無い。
もちろん
海外に移住出来るように
何かしておくとか
色々有るんでしょうけど
現実的に難しいですよね?
無駄な保険というのも
・がん保険
・学資保険
・養老保険
・外貨建て保険
・個人年金保険・・・
いっぱい
無駄な保険が有りますけど
これも結局
コストパフォーマンスが
悪いんですよ。
対策として
色んな事に備える
がんに対して備えるとか
外貨建ての投資をするとか
貯金を貯めるにしても対策として
コストパフォーマンスが
悪いんですよ。
持ち家にしても
持ち家=ダメというのではなくて
将来貸してくれないかもしれないから
という事だけを
理由に家を買うと
だいぶコストパフォーマンスが
悪いのではないでしょうか。
携帯電話とか格安SIMでもそうですね。
大手だと
何かあった時安心だから
変えないという人とかも
確かに大手とそれ以外の
格安SIMの会社だったら
どちらが盤石かと言えば
大手の方が
財務状況なんかは盤石ですけど
でもだからと言って
何かが有るか
その確率はどうか
という事ですよね?
格安SIMであっても
ちゃんと通話出来ます。
伝えたい事としては
コストパフォーマンスの悪い対策も
もったいないという事です。
〜〜〜つづく〜〜〜
Special Thanks college president Ryo.

●おまけ
≪≪perplexityちゃんによる文章まとめ≫≫
確率を無視した議論や対策は意味がなく、現実的な根拠や数字が伴わない話は、ただの空想に過ぎません。
「国が崩壊したらどうする?」など極端なリスクを心配して高額な保険や対策を取ることは、コストパフォーマンスが悪く、お金の無駄遣いにつながります。
例えば、将来家を借りられなくなるかもしれないという不安だけで持ち家を購入したり、大手携帯会社の安心感だけで高い料金を払い続けるのは非効率です。
重要なのは、そのリスクがどれほど現実的か、対策にかかるコストが妥当かを冷静に考えることです。
不安に流されて過剰な備えをするのではなく、確率や費用対効果を意識した賢い選択を心がけるべきだという主張です。
[1] https://riss.aist.go.jp/research/20230802-2648/
[2] https://www.minjiho.com/book/b10093474.html
[3] https://note.com/valueqa/n/n62761f9efc70
[4] https://100years-company.jp/column/article-960115/
[5] https://dlpo.jp/ab-test/ab-test5.php
≪≪Chat-GPTくんによる英訳≫≫
〜Continuing from Last Time〜
【Arguments that ignore probability are just science fiction. — Bring the numbers.】
> “What if the country collapses? That’s possible, right?”
>
> “Well, sure, it’s *possible*.”
>
> But if we start going down that road, it becomes:
>
> “Isn’t it possible I could die tomorrow?”
>
> That kind of talk leads nowhere.
Then there’s this:
> “What if you can’t rent a place in the future?”
Sure, that might happen.
But it also might not.
You could just as easily say,
“Maybe someone will rent to me.”
Then there’s the classic:
> “If inflation keeps rising, you’ll regret not owning a home.”
Or the ever-popular:
> “My investments are giving me 20% returns!
>
> Index funds only give you 6–7%, right?
>
> But here’s how I do it — 20%, no problem!”
These arguments all ignore probability.
Whenever someone ignores either range or probability,
the discussion loses meaning.
No matter how long you argue — it’s just empty talk.
—
【Countermeasures that ignore probability are just expensive self-satisfaction. — Stop burning money on fear.】
Taking action without considering cost performance is a waste.
Even if “the country collapses,”
there’s no high-cost-performance way to prepare for that.
Sure, you could prepare to move abroad,
but realistically — is that even feasible for most people?
Let’s talk about insurance:
Cancer insurance
Education insurance
Endowment insurance
Foreign currency-based life insurance
Private pensions
… and so on.
There are so many unnecessary policies out there.
At the end of the day, they’re all just
low-cost-performance ways to manage anxiety.
Same goes for other “just in case” actions:
Buying foreign-currency assets
Over-saving out of fear
Buying a house just because “what if I can’t rent in the future?”
Owning a home isn’t bad in itself —
but buying only because of fear of an unlikely future?
That’s poor value.
Same goes for mobile plans.
Some people refuse to switch from major carriers, saying:
> “I want the peace of mind in case something happens.”
Sure, big carriers have better financial stability.
But what’s the actual probability something will happen?
Even budget SIMs work just fine.
—
🟡 Bottom line:
Wasting money on low-probability fears is just bad economics.
If your “protection” lacks logic and numbers,
it’s not safety — it’s self-indulgence.
Special Thanks OpenAI and Perplexity AI, Inc